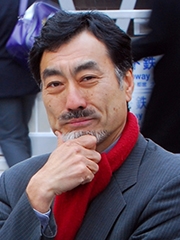| 12月4日(水) | 11:40〜12:00 |
[P-01]「温室効果ガス削減、健全なインフラを未来に託す」ヤマダインフラテクノス 技術管理部 課長 深谷 亘氏 |
|---|---|---|
| 13:40〜14:00 |
[P-03]「インフラ老朽化点検の低コスト化と作業効率向上」倉敷紡績 画像情報課 原田 仁氏 |
|
| 14:20〜14:40 |
[P-04]「UAVを活用した橋梁点検ソリューションについて」デンソー 社会ソリューション事業推進部 UAVシステム事業室室長 村端 秀峰氏 |
|
| 15:00〜15:20 |
[P-05]「道路の維持管理効率化に向けた評価診断技術開発への取り組み」清水建設 技術研究所社会システム技術センター 主任研究員 稲田 裕氏 |
|
| 12月5日(木) | 11:40〜12:00 |
[P-06]「将来の高速道路マネジメント-i-MOVEMENTプロジェクト~」中日本高速道路 保全企画本部 次世代保全推進課 課長代理 吉谷 直人氏 |
| 13:00〜13:20 |
[P-07]「インフラの点検会社が考える-情報の見せる化技術」アイセイ 技術開発部空間情報グループ主任 藤田 吉臣氏 |
|
| 13:40〜14:00 |
[P-08]「耐塩害性に優れる錆転換型防食塗装 アースコート防錆塗装システム」三重塗料 副社長 湊 久幸氏 |
|
| 14:20〜14:40 |
[P-09]「ドローン測量サービス『くみき』の紹介」朝日航洋 UAS事業推進部 茨木 康広氏 |
|
| 15:00〜15:20 |
[P-10]「インフラの調査点検・補修・更新技術 ~大林グループの取り組み」大林組 土木本部生産技術本部 リニューアル技術部 青木 峻二氏 |
|
| 12月6日(金) | 11:40〜12:00 |
[P-11]「インフラ点検のスマート化~画期的なさび検出方法のご紹介~」エネルギア・コミュニケーションズ 情報システム事業本部開発センター サブマネジャー 佐藤 靖氏 |
| 13:00~13:20 |
[P-12]「はかるの先を実現」ソーキ 企画部マーケティングG グループリーダー 中野 武博氏 |
|
| 13:40~14:00 |
[P-13]「道路・鉄道・空港などの運営、管理を支援するアセットマネジメント」オリエンタルコンサルタンツ 道路整備・保全事業部 副事業部長 猪爪 一良氏 |
|
| 14:20~14:40 |
[P-14]「橋梁点検におけるドローン利用と3次元管理」日立システムズ ドローン・ロボティクス事業推進プジェクト 部長代理 宮河 英充氏 |
|
| 15:00~15:40 |
[P-15]「IoTによる屋外設備や環境のモニタリングサービス紹介」日本ユニシス 新事業創出部PFイノベーション室 岡村 祐希氏 |
12月4日(水) 11:00~12:00 【インフラメンテナンス国民会議地方フォーラム 各地方フォーラムの取り組み紹介】
申込番号:I-01【インフラメンテナンス国民会議地方フォーラム 各地方フォーラムの取り組み紹介】
| 会場 | カンファレンスステージ |
|---|---|
| 受講料 | 無料 |
◆中部フォーラム「官民連携の仕組みの導入に向けた検討」
オリエンタルコンサルタンツ 中部支店構造部次長 安藤 誠氏
◆近畿本部フォーラム:官民マッチング事例
一般社団法人 国土政策研究会 板倉 信一郎氏
◆ちゅうごくフォーラム「市民との協働事例」

岡山県立岡山工業高等学校 進路課土木科 教諭 狩屋 雅之氏
(略歴)
インフラ管理者だけが維持のサービスを行う現在の仕組みを見直し、インフラ利用者である様々な立場の人たちがインフラメンテナンス問題に参加していくことが「活力ある社会の維持」に必要であると考えた。本取組は道路管理者である国土交通省岡山国道事務所、その管内の維持工事受注三企業、インフラ利用者として県内土木科設置三工業高校の取組みとして『岡山道路パトロール隊』の活動を行った。三者がクラウドサービスを通じて情報共有することにより、交通弱者といわれる歩行者や自転車の利用者に対し早急な道路管理が行えた。また担当した高校生は社会貢献に目覚める事ができた。
◆九州フォーラム「フォーラム活性化の取り組み事例」

福山コンサルタント 代表取締役社長 福島 宏治氏
(略歴)
九州フォーラムの活性化事例として、①ピッチイベントの工夫。②自治体支援の体制づくり。③広報活動の工夫事例を紹介する。ピッチイベントを九州全域へ展開するための第一歩として大分県内の各関係機関を集めた新たな実行委員会を組織し、全自治体を訪問しニーズを収集した結果、多くの自治体の参加が得られた。自治体支援では、「シニア・テックグループ(仮称)」として自治体が抱える課題について、技術アドバイスを行う新たな組織を設立した。広報活動では現場レポートを通じ、親子で学びながら、インフラメンテナンスの意義と魅力を実感してもらうイベントを実施しPR動画の成果を得た。